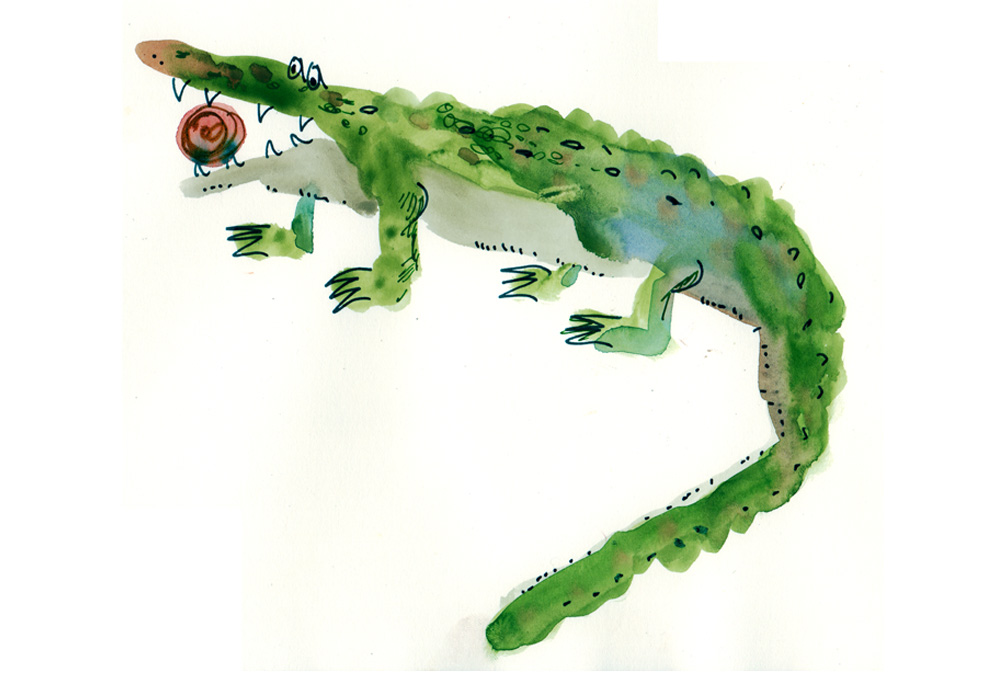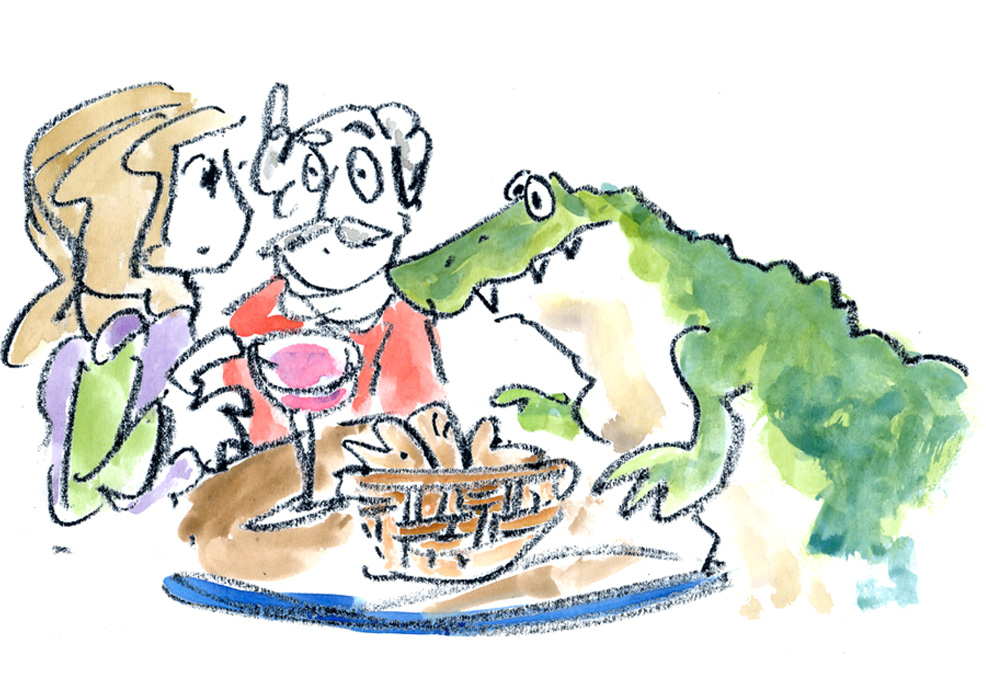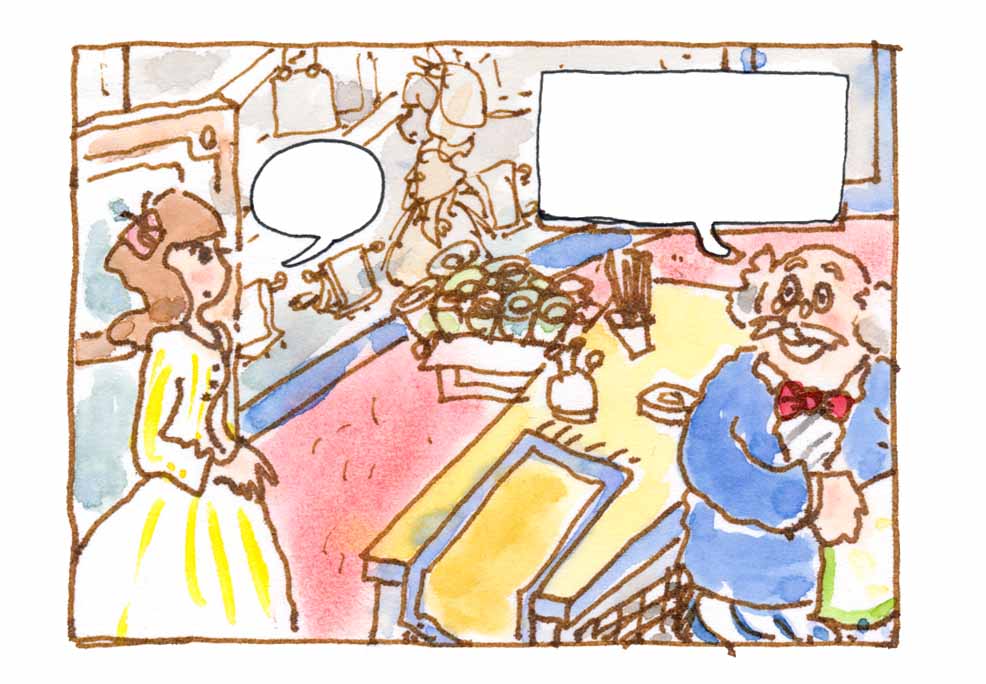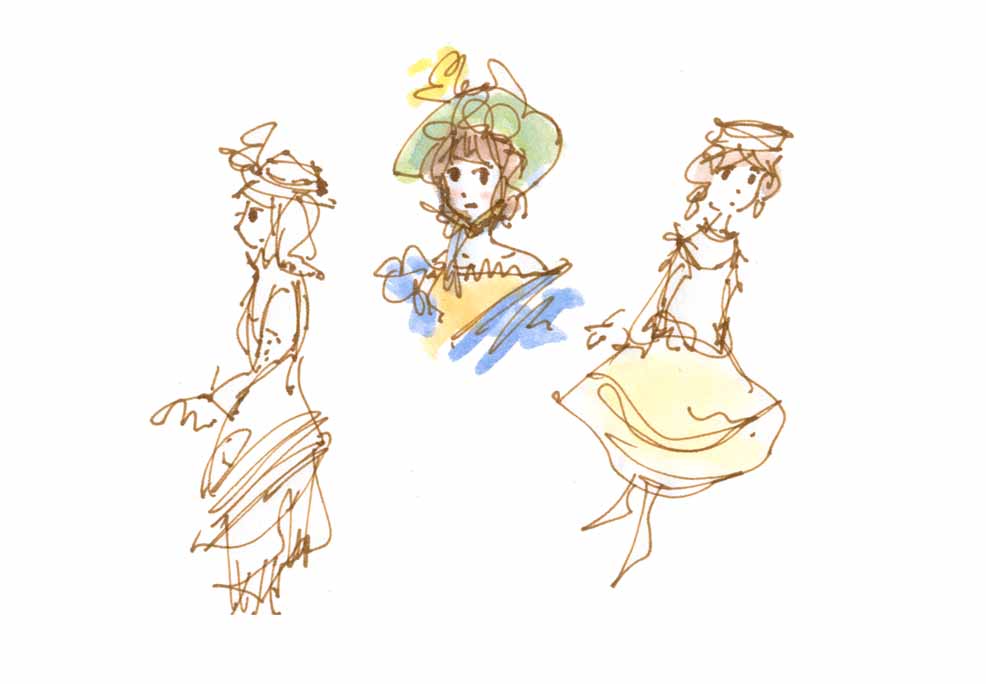|
|

 むにゃむにゃなムニャムニャ 作品になる前のむにゃむにゃした絵と、考えになる前のむにゃむにゃした言葉を、むにゃむにゃとかきとめておく。 上のカエルは、らっぱを吹いているところ。食べているのではないですよ。 2011 / 2012 / 2013-2015 / 2018- / むにゃむにゃしおえる
ここに書くのがずいぶん久しぶりになってしまった。というのも、七月の後半からグループ展の準備に追われ、なんとか間に合ったと思ったら、今度は年末の個展まであまり余裕がない、という事態になっていたからなのだけど、でも、その間にも色々と考えたことや収穫がないわけではなかった。
中でも大きいのが、アルピニズム、登山に関する本に出会ったこと。雑誌「考える人」のメールマガジンで、映画「運命をわけたザイル」が紹介されていたのがきっかけで、映画の原作『死のクレバス』(ジョー・シンプソン)を読んだ。以前、『エンデュアランス号漂流』というノンフィクションを読んで、いたく心を動かされたのだけど、仲間同士で罵り合い、助け合いながら生き抜こうとする『エンデュアランス号漂流』に対し、『死のクレバス』はまったき孤独の中で死と向き合うという、とても恐い体験の記録だった。 それを読んだ後、タイミングよく雑誌『Terminal』が出たので、それを買う。これがまたなかなか面白かったので、続けてラインホルト・メスナー『ナンガ・パルバート単独行』を読み、続けてガストン・レビュファ『星と嵐』『星ののばされたザイル』『山こそ我が世界』を手に取った。 ぼくは山に登るのが大嫌いなので、これらのいい本を読んでも、自分が登りたいとは思わないのだけど(アイスピッケルとザイルは欲しくなった)、自分が山登りに一向にひかれないせいか、どうして彼らが山に登りたくなるのか、ということがわかりたくて読んでいる、ということがある。 そして未だにその理由はわからない。レビュファが寒さに凍えつつもピバーグの楽しさを朗らかに書いている部分など、絵にしてみたい気は湧き起こってくるのだけど、どうしてそんなところで、と思うような場所で一夜を明かす彼らに、ユーモラスな姿を見てしまいもする(もちろん、そこにユーモアが入り込む余地があるように書いているところに、レビュファの登山家としての、そして書き手としてのすごさを感じるのだが)。 結局、ここまで読んできて、登山というのは山との孤独な戦いであったり、登頂するということ以上に、そこまでのプロセスが重要であったり、でもやっぱり登頂するのが一番大切だったり、また、その都度自分がその山をどう登るのか、ということが問われることであったりということが、頭ではわかってきて、ともすると、自分が絵を描く、ということと結びつけて読んでしまいそうになることがある。でも、簡単に自分と結びつけないで、もうちょっと原石のまま、自分には未だ理解できない謎のままの形で、読み進めていきたい。 わかる部分をわかってしまうよりは、わからないことを含めてわからないままにしておく方が、実り多いこともある.…… ということだろうか。 2012/10/3
ここに書くのがずいぶん久しぶりになってしまった。というのも、七月の後半からグループ展の準備に追われ、なんとか間に合ったと思ったら、今度は年末の個展まであまり余裕がない、という事態になっていたからなのだけど、でも、その間にも色々と考えたことや収穫がないわけではなかった。
中でも大きいのが、アルピニズム、登山に関する本に出会ったこと。雑誌「考える人」のメールマガジンで、映画「運命をわけたザイル」が紹介されていたのがきっかけで、映画の原作『死のクレバス』(ジョー・シンプソン)を読んだ。以前、『エンデュアランス号漂流』というノンフィクションを読んで、いたく心を動かされたのだけど、仲間同士で罵り合い、助け合いながら生き抜こうとする『エンデュアランス号漂流』に対し、『死のクレバス』はまったき孤独の中で死と向き合うという、とても恐い体験の記録だった。 それを読んだ後、タイミングよく雑誌『Terminal』が出たので、それを買う。これがまたなかなか面白かったので、続けてラインホルト・メスナー『ナンガ・パルバート単独行』を読み、続けてガストン・レビュファ『星と嵐』『星ののばされたザイル』『山こそ我が世界』を手に取った。 ぼくは山に登るのが大嫌いなので、これらのいい本を読んでも、自分が登りたいとは思わないのだけど(アイスピッケルとザイルは欲しくなった)、自分が山登りに一向にひかれないせいか、どうして彼らが山に登りたくなるのか、ということがわかりたくて読んでいる、ということがある。 そして未だにその理由はわからない。レビュファが寒さに凍えつつもピバーグの楽しさを朗らかに書いている部分など、絵にしてみたい気は湧き起こってくるのだけど、どうしてそんなところで、と思うような場所で一夜を明かす彼らに、ユーモラスな姿を見てしまいもする(もちろん、そこにユーモアが入り込む余地があるように書いているところに、レビュファの登山家としての、そして書き手としてのすごさを感じるのだが)。 結局、ここまで読んできて、登山というのは山との孤独な戦いであったり、登頂するということ以上に、そこまでのプロセスが重要であったり、でもやっぱり登頂するのが一番大切だったり、また、その都度自分がその山をどう登るのか、ということが問われることであったりということが、頭ではわかってきて、ともすると、自分が絵を描く、ということと結びつけて読んでしまいそうになることがある。でも、簡単に自分と結びつけないで、もうちょっと原石のまま、自分には未だ理解できない謎のままの形で、読み進めていきたい。 わかる部分をわかってしまうよりは、わからないことを含めてわからないままにしておく方が、実り多いこともある.…… ということだろうか。 2012/10/3
昨日の友人(写真家)との会話での収穫。イメージ(写真や絵)は表面に軽く触れることができ、言葉は深くもぐることができる。このことがより確信に近付いた。
これについては、古代ギリシャで提起され(「絵は無声の詩、詩は有声の絵」)、レッシングが反論した問題とあわせてより詳細に考えてみなければいけないことだろうけど、考える際の出発点となる自分の足場ができたのはいいことだ。 ところで、レッシングが挙げる時間芸術と空間芸術の区別は、なかなか便利な考え方だけれども、その反面、便利なだけに気をつけないといけない、とも思う。「時間芸術と空間芸術」という言葉を使っただけで、何かを考えたつもりになることがあると、よくない。 というのも、時間の流れていない空間などないのだし、空間を持たない時間もまたないのだから。存在するということは、時間が空間を獲得することだ。 ぼくはオクタビオ・パスに同意して、絵も詩も共に詩である、と思うけど、分離はできないが区別することはできる、とも思う。その区別の際に、表面に軽く触れるイメージと、深くもぐることができる言葉、という特徴が手がかりになってくれるのではないか、と期待。 それに区別すること以上に、イメージと言葉の組み合わせ、「お互いに相手を信頼して、かつ必要としている」というあり方、これに進んでいきたい。 2012/7/10
重要なヒントはいつも自分の一番近くにあるようだ。さんざん歩きまわった後で、疲れて足元を見るとすっとみつかる。
ポップスであれ、クラシックであれ、同じ曲を他の人がカバーしているのを聴くと、自分はとてもわくわくするということ。これを忘れていた! 2012/7/5
同じ絵でも、水彩絵具で色をぬるのと、パステルでぬるのとでは違った絵になる。
インクで線を描いて、絵具で色をぬるにしても、それをどんな紙に描くのか、でまた違った絵になる。 ところが、同じ画材で、同じ紙に描いても、描くときの筆圧を変えるだけで、違った絵になることには気が付かなかった。改めて考えると、そりゃあ違う絵になるだろうな、とわかるのだけど。 絵だけではなくて、世界を眺める視線にも、この「筆圧」のようなものがあるのだろうか。 2012/6/25
好きな本を読む。それがすごく好きな本であるとわかったり、あるいはもっと進んで、自分を変えてしまうような本だったりする場合、その本は繰り返し読まれることになる。
どんなに好きな本でも何度も読み返すうちに、ちょっとずつ読んで得られる刺激が少なくなっていく。読み方も雑、というか、とばしとばし読みたいところだけ読んでいくようになる。 気が付くと、その本に書かれていたことが自分の認識の一部になっていることに気が付く。どこからが自分が考えたことで、どこからがその本から学んだことなのか。からまりあった木の根っこみたいに、わからなくなっている。 本の内容はすっかり自分の中に移ってしまっている。目の前にある、本の形をしているものは、実は「本の抜け殻」なのだ。お気に入りの本が並んだ棚の前にて。 2012/6/20
ぼくの好きな哲学者が、若いときに行った講義の中で「生とは自らに留まりながら、自らを超えていくことだ」と述べている。
この場合の「生」とは、人間やライオンとかの動物はもちろん、植物、さらには石や砂、つまり存在しているものすべてを含んでいるのが面白いし、それだからこそ、この言葉を核に一つの「生の哲学」を展開することが可能になる(その講義は、まさにそれを試みたものなのだけど、成功しているとはいえない、とぼくは思う。その失敗をもってしても、有り余るほどの思想的な豊かさがその講義には見出せるのだが)。 ところで、「自らに留まりながら、自らを超えていくこと」というのは、絵を描いているときによく感じることだ。同じモチーフでも違う方法で描いてみる。あるいは、今までと同じ方法で、でも違う表情に描いてみる。それは自分の表現を拡張していくことだ。 でも、それをやっていくと、自分の描いていたもの、描くときに大切にしていたものがわからなくなってしまう、ということが起こる。それで、今まで描いていたものの方にもどっていこうとする。そうすると、結局、今まで変わらないから、また試す。 この留まることと、超えていくことの緊張の中から、新しくて面白いものが生まれてくればいいのだけど。と、ここで、ふと石にもその緊張関係が見出せると思うと、はっと思いつつ心がなごむ。 2012/6/5
ヴァルター・ベンヤミン『パサージュ論』の「目覚め」について。今回は長いよ〜。
『パサージュ論』を原案にした漫画を描くにあたって、取り組まないといけない問いはたくさんあるけれども、その中でも描き始める前にどうしても(とりあえずであれ)自分なりの答えを出しておかないと進めない、と思っていたのが、この「目覚め」についてだ。ベンヤミン自身が述べているのに同意して([N4,3])、「目覚め」は『パサージュ論』の試み全体を特徴付けるものだと思っていたから。 「目覚め」について考える上で、ヒントになるものは私見によれば、三つある。(i) プルーストによる「目覚め」、(ii) アラゴン『パリの農夫 Le paysan de Paris 』、(iii) プルーストの方法(想起)。三つといいながら、ほとんどプルーストだね。(以下、『パサージュ論』からの引用は、岩波現代文庫版より。[...] はぼくによる略)
「プルーストがその生涯を目覚めのシーンから始めたのと同様に、あらゆる歴史記述は目覚めによって始められなければならない。[...]こうしてこのパサージュ論は十九世紀からの目覚めを扱うのである」(N4,3)
プルーストが個人的な生に対して行ったことを、ベンヤミンは十九世紀のパリに対して行おうとしていた、ということがうかがわれるテキストだけど、さらに進んで、ベンヤミンが「目覚め」について、プルーストから学んだことについて見てみる。それによれば「目覚め」とは、「夢の意識というテーゼと目覚めているという意識というアンチテーゼの統合」([N3a,3])であり、「目覚めの瞬間」こそが「認識の可能となる今の時」([N18,4])だとベンヤミンは書いている。いいかえれば、「目覚め」とは、夢の中に完全に浸っている状態と、夢から完全に切り離された状態の境界であって、そここそが夢と距離を取りつつ夢を認識することが可能な場だ、ということだろう。 『パサージュ論』を構想するに当たって、ベンヤミンがインスピレーションを得た一つがプルーストだとすれば、もう一つがアラゴンの『パリの農夫』だ。この著作の中でアラゴンは、見慣れたパリをもう一度、新鮮な目で捉えた上で、シュールレアリスティックな幻想と混ぜ合わせて一個のヴィジョンに仕立てていく。最もありふれたものの中から、最も驚きに満ちたイメージを取り出すという『パリの農夫』の特徴は、そのまま『パサージュ論』の特徴ともいえそうだけど、ベンヤミン自身は次のような区別をつけている。
「[...]アラゴンが夢の領域に留まろうとするのに対して、私の仕事では覚醒がいかなる状態であるのかが見出されなければならない。アラゴンの場合には、印象主義的な要素――それは「神話」と言われる――が残されている。彼の著作には、明確な形姿を持たない哲学的思考要素がさまざまあるが、それはこの印象主義によるものである。これに対して私の仕事では、「神話」を歴史空間の中へと解体しきることが問題なのである。それは、過去についての未だ意識化されていない知を呼び覚ますことによってのみ可能である」([N1,9])
というわけで、先にプルーストのところで書いてしまったけれども、ベンヤミンによれば、アラゴンの著作は夢を見ている段階にあるのに対して、『パサージュ論』は「目覚め」から夢を扱う、そこが違う、ということになるだろう。 では、肝心の「目覚め」から夢を扱う、とはいかなる方法によって可能になるのか。ベンヤミンはその方法について「歴史認識」という言葉で度々言及している(例えば「過去の一片がアクチュアリティに撃たれるためには、両者のあいだに連続性があってはならない」([N7,7])。その「歴史認識」についての最大の成果物がいわゆる『歴史哲学テーゼ』だけど、あのテキストを含めた『パサージュ論』全体の歴史認識の方法を、理解・解釈するに当たって、プルーストにもう一度立ち戻ることは非常に有益だとぼくは思う。
「[...]プルーストが個人として追悼的想起という現象に即して体験したことを、われわれは[...](十九世紀までさかのぼって)、「潮流」とか「モード」とか「動向」として経験せざるをえないのである」(K2a,3)
これらの引用を読むことによって、ベンヤミンは『パサージュ論』という試みの中で、プルーストから「目覚め」だけでなく「想起」という二つを受け取っているがわかる。いってみれば、「目覚め」が認識の場であるとすれば、「想起」とはその認識の方法なのだ。
「[...]体験された出来事は有限であり、少なくとも体験というひとつの領域に包み込まれているのに対し、追想される出来事は、その前後に起こった一切の事柄に対する鍵にほかならないがゆえに、限界をもたないのだ」(「プルーストのイメージについて」『ベンヤミン・コレクション2』筑摩学芸文庫)
ぼくが理解していることによれば、これこそがベンヤミンがプルーストから学んだ「想起」の方法の根本原理だ。あるいは、こういうこともできるだろう。すなわち、過去は時間的には有限であるが、想起においては無限である。これがベンヤミンが歴史的事象の「モナド的構造」と呼ぶものの正体であり、「歴史的事象はみずからの内部に自分固有の前史と後史が写し出されているのを見出す」([N10,3])理由でもある。 マルセルがジルベルトに対して抱いた最初の嫉妬を想起するとき、その嫉妬という出来事は、想起しているマルセルが今ここにおいて、このマルセルであることを示す鍵であると同時に、その嫉妬以前のマルセルが収斂していく点でもある。同様に、パサージュという具体的な事象は、パサージュを知らなかった世界が向かっていく終着点であると同時に、それを認識しようとする「今ここ」における私の根源であるのだ。それは、パサージュという具体的な(ということは有限な)形態が非完結的に指し示していた「意味」の探求に他ならない。 さて、以上のことをまとめながら、自分の言葉で再構成していこう。「目覚め」を核にして見えてくるベンヤミンの企てた『パサージュ論』の目指すものとは、パサージュという具体的な形態の中に表現されていた「意味」の展開だ。この「意味」を意識的に開示しようとはせずに、形態の持つ不思議さ、面白さに魅了されること、これがアラゴンの著作に見られる「夢見る」段階であり、ベンヤミンの企てとの違いである。 具体的な形態の持つ「意味」の探求。これを具体的な形態を抜きにして展開しようとするのが、直接的に神学的な方法であろうけれども、それは形態の持つ具体性と一回的な意味深さを見落としてしまうだろう。直接に神学を展開することを回避した上での、「意味」の探求。それは表面的には神学ではないが、「意味」の探求である以上、つまり、具体的な形態の持っている意味の「意味」の探求である以上、「私たちは、歴史を原則的に非神学的に捉えることが禁じられるような経験をするのだ」([N8,1])。 ちょっとした余談だけど、このことからなぜ『パサージュ論』およびベンヤミンの諸著作の中には、肝心の神学の具体的な内容が書いていないのか、ということが明らかになる。『パサージュ論』が歴史的事象の具体的な形態の持つ意味の「(根源的)意味」の展開を目指していたとすれば、神学がその答えになるわけだけど、神学を神学として展開したとすれば、それはまた別の「意味」としてのみ展開可能であって、「意味の意味の意味の[...]探求」という形の不毛な試みとなるか、あるいは抽象的な体系の構築となるか、のどちらかしかない。 そうした不毛な探求ではなく、かつ具体的であることを求めるのであれば、意味の「意味」の探求は、具体的な事象の中で「意味」が無意味に打ち勝つプロセス、およびその構造の記述によってのみ可能だと思う。パサージュの発展と荒廃。その具体的なプロセスの記述こそがベンヤミンの神学の場だったのだろう。 2012/5/2
ぼくには気が散るところが多分にあるようで、絵本に取り組んでいると、今描いている絵本とは関係ない絵が描きたくなる。あるいは、今取り組んでいるのとは別の作品のアイディアが浮かんでくる。
少し前に「それなら、もしかしたら」と思って、性格の違う二つの作品に同時に取り組むことにした。これはなかなかうまくいっているようだ。 〆切が近いときはどうしても一つに集中しなければいけないのがつらいところ。 2012/4/21
本屋で見かけて、何となく気になったので買った『ベイリー、大好き』(著:岩貞るみこ、写真:澤井秀夫、小学館)という本。これが、ああ! とてもすてきだった。一度読んでからも、また手に取って少しずつ読み返したくなる。
静岡県立こども病院の小児病棟で働く、セラピードッグのベイリーとハンドラーの森田さんの様子を綴ったノンフィクションだ。ひとつひとつのエピソードは本書にゆずるけれども、「ベイリーが来たよ」と聞くと、ベッドで寝ていた子供がベイリー見たさに自分で体を起こそうとする。ぱっと子供の顔が明るくなる。 「ベイリーはこどもの持っている力をひきだしてくれるんです」本の最後の方に出てくる看護婦さんの言葉を読んで、うーんとうなる。これは子供との一つの理想的な関係ではないだろうか。 読んだ子供の気持ちが、ぽっと温かくなる。わくわくして体を動かしたくなる。そんな絵本をぼくも作りたいなあ。 2012/3/24
ヴァルター・ベンヤミンの未完の遺作『パサージュ論』をベースにした漫画を描いた(Art Critique n.02)。『パサージュ論』の面白さに魅了されてから、その内容をヴィジュアライゼーションするという形で表現できないか、といつしか思うようになった。そういう意味では何年も温めてきた企画だけど、今回描けたのは、イントロダクションのイントロダクションのような内容で、ページ数も4ページと少なく、まだ満足いくものには程遠い。まあでも、このような大変なプロジェクトはやや強引に始めるでもしないと、いつまでも取りかかれないものなのかもしれないので、とにかく描き始めることができてよかった。
それにしても『パサージュ論』ほど、知的好奇心を刺激する著作も少ないだろう。ベンヤミンが書こうとしていた大著のアイディア・メモの固まりなので、ベンヤミンによる完成稿を読みたかった、と口惜しく思うのと同時に、草稿に留まったからこそ、読む人にどこまでも開かれている著作だとも感じる。 それに扱っている内容がまた面白い。二度の世界大戦を経験する前夜のヨーロッパと、その中心で輝いていた大都市パリ。爛熟した文化と、まだ夢見心地であった資本主義と科学の世界。その地下に流れる怪しく黒い水脈.... 多様な現実と可能性が複雑に絡まりあった19世紀パリの姿を、ベンヤミンは一見ささいな具体的事象を見つめることによって取り出そうとする。 さて私見では『パサージュ論』の最大の特徴は、ベンヤミンがこの仕事の中核に、意識的に神学を導入していたことだ(例えば、『パサージュ論』[N2,1]、[N7a,7]および「歴史哲学テーゼ」1を参照)。神学的に歴史を認識しようとすること。それは過去と現在を含めた、現実の積極的な解釈であると同時に、そこにおける「罪」や「救済」について想いをめぐらすことだろう。つまりそれは、歴史的な事象を客観的に眺めるという態度ではなくて、歴史的な事象という客観の中に、認識しようとする主観自体が巻き込まれている、そういう切実で必死な認識態度だ。ベンヤミンは『パサージュ論』の採用する歴史認識の哲学的ライバルに、ハイデガーの名前を挙げているが、それもそのはずで、ベンヤミンの歴史認識もまた「実存的」と呼べるものだったからだと思う。 (では、両者の最大の違いは、といえば、『存在と時間』の中で展開されているような形で、人間の実存の置かれている「罪」的な側面をハイデガーが強調したのに対して、ベンヤミンは「救済」についてもっと積極的に考えたかったのだと想像する。それにハイデガーの説く、孤独に決断する個人に対して、ベンヤミンは集団的な連帯の可能性について考えていたのかもしれない。ぼく自身は孤独な個人と集団の間の、「自己と他者」という形で考えを進めてみたいと思っているが。) どこまでも具体的なものに留まって思考しようするという意志。しかしその背後で思考を動かしている神学。両立できなそうなこの二つの歯車を噛み合わせようとするベンヤミンの「始まろうとする思考」の気配が、『パサージュ論』の魅力の源になっているように思えてならない。 ここで本当に書こうと思っていたのは、「パサージュ論は19世紀からの目覚めを扱う[N4,3]」というときの「目覚め」とは何なのか、についてだったけど、長くなるので今日はこのへんでムニャムニャして終わることにしよう。 2012/3/21
ものしか出てこない小説、つまり、人間が登場しない小説を書くことはできるか。
小説でも漫画でもいいけど、ある作品を読んでこれをアニメーション映画にするにはどうしたらいいか、ということを考えるのがイマジネーションとクリティックのいいトレーニングになるように、ものしか出てこない小説について考えるのも、作品ということを考える上でいい訓練になる。 ものしか出てこない小説の難しい点は、人間が関心を寄せるのは人間だ、ということがまずある。ものしか出てこない小説とはいえ、ものに流れている時間をそのまま描写するのでは数式や物理法則の羅列のようなものになってしまい、鑑賞できる作品にはならないだろう。でも、逆にいえば、ものに人間的な時間や空間を与えることはできる。これは一つのヒントになる。 ものに人間的な時間を流したり、人間的な空間の中に置く、ということは、ものを擬人的に扱う、ということではない。それでは人間が登場する作品の一変種になってしまう。では、誰かある人の持ち物だったことのある「もの」というのはどうか。例えば、少年に拾われたことのある、今は野原に転がっている小石。ここが「人間が登場しない」と「登場する」の境界線だろう。誰かの持ち物だったことをどう書くかによって、そのどちらにもなりうるから。 もう一つのヒントだと思うのは、延々と同じものを撮り続けたアンディ・ウォーホルの映像作品だ。ウォーホルの意図が何であれ、そこに写っているものは現実そのものでもなければ、意識的なフィクションでもない。それは現実ほどリアルではなく、ちゃんとした作品ほどリアリティーがない(「ちゃんとした」というのは我ながら荒っぽい言い方だね)。 いってみれば、作品とは小説であれ、絵本であれ、映画であれ、現実の抽象化という要素を多分に含んでいるといえると思う。ものしか出てこない小説にもどって考えると、その小説が扱うのは、ものの置かれている現実ではなく、ものが持っているリアリティーの方だ。ものの置かれている時間と空間を具体的に描きつつ、かつそこに留まっていてはいけない。 そうなると、ものしか出てこない小説は、詩に近付いていくような気がする。今ここにものが存在しているという、時間と空間の描写、ものが持っている記憶(擬人的にではなく、時間と空間を文章によって跳び越すことによって)、すれ違う人間や動物達、草の足元に転がっている小石、そのはるか頭上に輝く星々。かわいた風がふくように、世界を眺めること。 2012/3/14
オクタビオ・パスは芭蕉『奥の細道』に出会って、俳句と散文の使い分けに目を引かれた、と書いていた。大学生のときにこれを読んでから、詩と散文の組み合わせというテーマがずっと引っかかっている。もちろん、『奥の細道』の散文はいわゆる散文というよりもむしろ散文詩に近いのだろうけど、散文で書き始めてから一句詠む、というあの形式は確かに面白い。
それから数年たって、『冬の日』というアニメーションを観た。これは連歌『冬の日』を大勢のアニメーターが合作でアニメ化し、アニメーションで連歌をやろう、という作品。芭蕉の発句をノルシュテインが担当している(またも芭蕉だ!)。ノルシュテインは芭蕉と竹斎に触れて、芭蕉を詩の人、竹斎を散文の人だという。そして、詩的なものは散文的なものの積み重ねの中にあるのだ、とも。これを読んだとき、詩と散文の組み合わせ、というものが、単に文学上の形式に関わるものではなくて、生きること、生き方そのものに関わっている問題なんだ、と遅ればせながら気が付いた。 さて、つい先日、オクタビオ・パスが生前に書いた最後の著作『インドの薄明』を久しぶりに読み返した。以前は面白いと感じた章がそれほど刺激的でなく、逆に以前はまったく興味をひかれなかったクリシュナに関する章がとても面白くて、それも興味深かったのだけど、何より「エピローグ」を読んでいてはっとしてしまった。 ここでパスは自分がインドを離れる前に訪れた場所について書いている。自分がこれらの景色を観るのもこれが最後だと考えながら、エレンファンタ島の海と空の青さに目を奪われる。エピローグは「その夜、ホテルへ帰ると、別れならびに祈りとして、私は次の詩行を書いた――」とあって、その詩が引用されて終わる。 引用されている詩は、インドでパスが書いた詩を集めた『Ladera este』に収められている「Domingo en la Isla de Elefanta -Invocación」だ。ところが、詩集の中でこの詩を読んでも大した感動は呼び起こされない。この詩がまさに詩としてたちのぼってくるのは、『インドの薄明』の「エピローグ」、パス生前最後の著作の、最後の文章の中の引用によってなのだ。 そこに書かれている散文という導入があって、初めてこの詩は「別れと祈り」という姿を現す。それでいて、この詩は散文の語る具体的な状況に縛られはしない。だからきっと、美しい別れに出会ったときにはこの詩句がぼくの唇からも流れ出てくることだろう。パスの最良の詩作品は散文詩『大いなる文法学者の猿』だと思っていたけど、ここにも散文と詩の組み合わせ、という形で一つあったというわけだ! 散文と詩。散文と絵。散文と日常。日常と詩、きらめき、祈り...... 考えなくちゃいけないことは、まだまだ多いみたい。 2012/2/26
レストランを舞台にした映画が好きだ。例えば、ローラン・ベネギ監督の『パリのレストラン』。テレビでやっていたのを何となくビデオに録画しておいたのだけど、渋くてどちらかというと地味なこの作品をもう何回も繰り返し観ている。
この前も、何か映画でも観るか、と思ってレンタルビデオ屋に行ったのだけど、手に取っては「これは今日の気分とは違うんだよなあ」と感じて、なかなか選べなかった。そうしたら『リストランテの夜』(スタンレー・トゥッチ監督)という作品にすっと目がいった。あらすじに目を通してから、これだ、と思った。終わり方には感心しなかったけど、切なくて、くすくす笑える、なかなかいい映画だった。 でもどうして自分はレストランの映画が好きなのだろうか。一つにはぼくが群像劇が好きだ、ということがあるかもしれない。レストランには料理を作る人、料理を運ぶ人、ワインを注ぐ人、食べる人、お客さんと様々な人が出てくる。その一人ひとりが欠かすことができない上に、一人ひとりが脇役だ。シェフが主人公だとしても、シェフがシェフになるのはお客さんが彼の料理をおいしそうにほおばったときなのだし、お客さんの誰か一人が主人公だとしたら他の映画になってしまうだろう(ジャック・ニコルソン演じる『恋愛小説家』のように)。お客さんはお客さんで、それぞれ自分の人生を生きている人がたくさんいるのがいいのだ。 それに何といっても料理。おいしそうな料理をみんなでワイン片手にガツガツ平らげていくのは爽快だ。食べる、ということは人間が生きていくことの根源に関わっているけど(高山なおみさんの文章のすごみはここから来るものだと思う)、その一方で、おいしい料理は会話を弾ませる。食べるという生の根源的活動と、出会いと会話を楽しむという文化的で精神的な活動。この二つが無理なく一体になっている場面を見ることができるのは最高に贅沢だ。 ディネーセンの『バベットの晩餐会』はいい小説だけど、料理と酒と会話を楽しむ客人達の描写では映画版にかなわないと思う。 そんなことを考えていたら、カスレとプリンを作って、晩餐会のようなことをしたいなあ、という気分になってきた。そういえば今年はインドカレーを作る一年にしよう、と決めたのに、まだ一度も作っていない。いやはや。 2012/2/22
昨日、誤って自分の眼鏡をふんずけた。慌てて手に取ってみたら、特に歪んでいるところもなかったので、普通にその眼鏡をかけて過ごしていたのだけど、夜になったら目がショボショボしはじめて、それでも寝る前に本を読んでいたら、ついに頭が痛くなった。そういうわけで、絵を描くときに使う度が弱い方の眼鏡を今日はかけているのだけど、目の前のものがぼんやりとしか見えない。
そういえば、前に行ったライブで、呼んでくれた人の知り合いの人が弾き語りをしていた。「私はもっぱら歌うのが専門で、演奏は下手なんですが、今夜は演奏もしちゃいます」といって、ピアノを弾き始めた。ピアノの演奏は、本人がいうとおり、本当に上手ではなかったのだけど、それを聴いているときになかなか興味深いことが起こった。 というのも、その人は流暢に歌いながら、たどたどしく弾くのだけど、そうすると、下手な演奏の中から、美しいメロディーが必死に出てこようとしているような印象を受けた。きれいな音楽が音のトンネルから出てこようとするのだけど、出口の穴が歪んでいるので、うまく出てこられない、というような感じ。 とすると、ぼく達が音楽に耳を傾けているときに聴いているのは、音自体ではなくて、それを通して伝わってくる「何か」ということかもしれない。オクタビオ・パスが「最もすばらしい詩とは、透明な詩だ」と書いていたけど、透明ではあっても、それを透かして向こうを見ていることには違いない。 ぼんやりした演奏のおかげで、こっちに来ようとしている音楽の気配に近付けたので、今のこのぼんやりとした眺めにも何か得るものがあるといいのだけど。 2012/1/23
映画が好きな友達と話していて、そういえば前にホセ・ルイス・ゲリン監督の『シルヴィアのいる街で』がいい、と他の友達がいっていたなあ、ということを思い出した。そこでその友達に聞いてみたところ「あの映画はいい」ということだったので、DVD を借りてきて観ることにした。
ガールズ・ウォッチングをしている主人公の男(ちょっとうっとうしい)がシルヴィアの後をつけて歩いていく。そうやって二人はいろいろな路地を通っていくのだけど、日陰にひっそりとある壁の一つ一つに、ちゃんと小さな窓がついている。ということはそこにも住んでいる人がいるんだなあ。 二人は何かしらの人ともすれ違う。一人ひとりが自分の用があって歩いている。こんなわけのわからない路地が、自分の生活の日常の一部になっている人が当たり前のようにいる、ということが面白い。何かちょっと特別なことをやっている気になっているうっとうしい男を横目に、全然特別じゃない時間が当たり前のように流れている。 ところで、この作品がいいと教えてくれた友人は「この作品は詩を撮っている」といっていた。どういうことだろう、と気にしながら観ていたのだけど、うっとうしい主人公とシルヴィアが大きな通りを歩いているシーンを観ていて、あっ! と思う瞬間があった。二人は割とせわしなく歩いているのだけど、カメラはそれをのんびり追いかけていく。詩はのんびりを好むということだろうか。例えば、そのときは遅刻しそうになって焦っていたとしても、その時間をのんびり思い出すときにはポエジーが訪ねてくるかもしれない、ということかな。うーん、とりあえず、この前買ってきたプアール茶をもう一杯飲んでこよっと。 2012/1/17
|
||||||||||||||||||